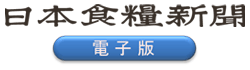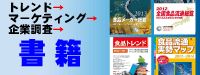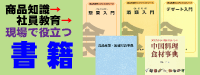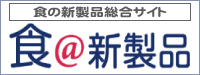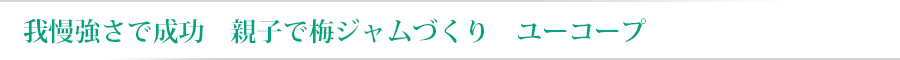生協には高い社会性が要求されている。だが、生協でも常に採算性という課題を抱えている中での活動のうち、全体で考えてできることから始めるという活動なのだ。地域の食料自給率の向上、福祉・小規模市場への対応、地域社会への貢献、環境保全活動などをまとめた。

熱いけど少し味見
「私がしゃもじでかき混ぜたい」「強火だけど大丈夫?」「なに?この白い固まり」――。子どもが次々と自分の親に要望や疑問を投げ掛ける。親たちは答えながら、調理を続ける。ユーコープは6月29日、梅の産地である小田原市下曽我にある梅の里センターで、収穫した完熟梅で作る梅ジャム講習会をJAかながわ西湘の梅部会・梅の香部会と共催。抽選で選ばれたユーコープの組合員6組が参加した。調理時間は約1時間半で子どもにとっては長い時間。飽きてしまった子どももいたが、我慢強い親の力で梅ジャムづくりに成功した。
ユーコープは、生産者と組合員で農作業や調理実習などを共同で体験するイベント「ヤマのがっこう」を年間を通して開催。練り梅、梅ジャムづくりなど梅関連のイベントはいつも好評で応募者も殺到するという。
梅ジャムは完熟梅を水から煮て金網のザルで果肉と種を分けて裏ごしし、砂糖を入れてしゃもじを入れながら煮詰めれば完成。一見簡単な作業だが、煮詰める時にかき混ぜ続けるなど手間暇をかけなければならない。
使い終えた調理器具の洗浄など進んで手伝う子どもがいる半面、飽きてしまって室内を歩き回る子どももいたが、最後は全組が成功。梅についての知識や知恵が身に付いたようだ。

組合員のために農業を行う(写真提供:生協ひろしま)
生協ひろしまは2010年に農業生産法人「ハートランドひろしま」を設立、障がい者の就労を支援しながら、組合員がいつでも農業の生産に触れることができる農場だ。生協ひろしまは産地直送(産直)事業などで広島県内の農業者と良好な関係を築いてきたが、さらに一歩進化した産直だ。
生協は農薬などの安全基準を守り、作業などを管理できる生産法人や農協と連携して産直事業を展開してきた。産直は組合員が農業者と交流することで、農産物がどうやってできるのか、農薬の必要性や安全性の保証などを学ぶ機会となり、これらが生協の農産物のリピーターにもつながる。
ひろしまも同様の取組みを実施していたが、2008年に日本生活協同組合連合会のコープ商品で中国製ギョウザ中毒事件が起き、組合員からも「信頼していたのに」など厳しい意見が続出。農業を知る機会をさらに増やすために農業分野への進出を決めた。
生協ひろしまは組合員の農業進出の要望を受け、生協の役割である社会的使命を果たすためにも、仕事上のストレスが発生しにくい農業で障がい者の就労を支援できる農業生産法人「ハートランドひろしま」を設立した。もともと交流のあった全国農業同組合連合会(JA全農)、地域の生産者に土地の取得の支援、栽培指導などを受けた。
通常の産直交流事では組合員の参加は収穫時期など限定的だが、滞在型などさまざまな交流スタイルが可能になった。販売も生協ひろしまの店舗や宅配の一部のみ。
液体肥料を使う養液栽培、ハウス栽培、路地栽培の3通りの栽培方法を実践していて、2015年度には面積もそれぞれ26a、65a、170aまでに広げていく予定だが、農業だけでは採算が取りにくい。障がい者雇用、組合員の交流の場と位置付けている。

おしゃれなカフェだが売上げ1位は焼きたてのみたらし団子

売店では介護食をエンド展開
コープあいち、全国大学生協連・東海ブロックは南医療生協に協力。2010年に開業した総合病院である南生協病院で協働事業を開始した。全国でも珍しい地域、大学、医療の3分野の生協の連携だ。今は病院内のレストラン、カフェ、売店を大学生協からの出向者が運営、コープあいちが要請したキユーピーの介護食、愛知県産トマトのアイス、愛知県産トマトケチャップの配荷など連携は第一段階だが、急速な高齢化を迎える社会で、生協の役割である地域貢献、組合員同士による助け合いの支援に加えて新たな事業の芽も出てきた。
南医療生協の活動は医療活動だけでなく、介護住宅の運営、街づくりなどにも及び、中核的な施設である南生協病院は健康増進のためのフィットネスクラブも運営、組合員同士による高齢者の見守りなどと幅広い保健、医療活動を行う。病院の1階にあるレストラン、カフェは通院、見舞いを含めた入院患者以外への飲食を提供。売店はおにぎり、カップ麺などCVSと同じような商品に加えて、患者が手術の時に使う専用の下着、介護食品など病院内ならではの商品も配置する。
病院の計画が出たのは08年。南医療生協がコープあいちにレストラン、売店などの運営をやってほしいと要請。病院の隣には大型のショッピングセンターがあるが、買い回りしづらい高齢者のワンストップショッピングに対応したかったという。コープあいちは店舗や宅配で商品を供給する購買生協で、レストランの運営ノウハウを持っていないことから、全国大学生協連を巻き込んで検討を開始。三者が出資して、社団法人「協働・夢プロジェクト」を設立、現在の形をつくりあげた。
病院内のレストランでは、配膳人に味の評価を伝えてくるなど反応がすぐに出るため、セルフサービスの大学生協の食堂とは異なる対応が迫られる。売店では、大学生協が取り扱う商品も配置するが、独自で調達先の開拓もしなければならなかった。新たなノウハウの蓄積にもつながっている。
また、「協働・夢プロジェクト」は、大学に寄付講座を設置して、農協を含めた協同組合の担当者が講義する。大学生によるボランティア活動、大学生協の経営に関与する学生委員が南医療生協へ就職するなど、連携による効果が交流という形でできあがりつつある。
連携の可能性はほかにもある。「協働・夢プロジェクト」の担当者はコープあいちが行っている高齢者見守りが、南医療生協も組合員同士による見守りと情報交換していけば地域により貢献できるという。また、アイデアの段階としながらも、コープあいちでも高齢者向けの食品の供給のノウハウの蓄積にもつながる可能性があるという。

大学生協もハラール対応 「うどん」「そば」も食べられます
イスラム圏からの留学生が増えている中、東京大学生協もハラール推奨メニューの提供に力を入れてきた。東京大学の本郷キャンパスにある第二食堂で5月26日、留学生が参加する試食会を開催。ハラール認証を受けた醤油などを使って、日本食の代表的メニューである「うどん」「そば」を提供した。
ハラール食品はイスラム教徒でも食べても良い食品。国によって微妙に異なるが、豚肉とアルコールはすべての国で認められていない。また、魚を含めた動物の調理も独特の手順が必要だ。
東大生協ではイスラム圏からの学生に対し、カレーやトマトを煮込んだ料理などを提供していた。また、学生もサラダのドレッシングなどを持参するなど不便だった。さらに「せっかく日本に来たのだから、代表的な日本食であるうどん、そばが食べたい」という要望が出ていた。そこで東大生協が参加する大学生活協同組合連合会が調整し、醤油、鰹節などでハラール認証を受けた食材を調達。消費者のニーズに応えるために事業連合が動くパターンだ。
醤油は製造過程でアルコール分ができてしまい、「つゆ」に欠かせないみりんもアルコールが含まれている。醤油はアルコールが製造過程でもできない商品を選択、みりんの代わりには砂糖などを使った。また昆布は問題ないが、鰹節はハラール認証を受けているタイの工場の製品を使用。うまみを多めにしたことで、通常の「つゆ」に負けない味にした。
試食会にはイスラム教徒ではない留学生も参加、味については申し分がなかった。「つゆ」ができたことで野菜の煮物、おでんなどにも活用が可能という。東京事業連合に参加する大学生協に広げていく。

環境配慮型の店舗 西宮の沢店

電気自動車専用の充電設備(西宮の沢店)

新聞紙、チラシ、段ボールの回収拠点。専門の業者が収集する(西宮の沢店)

七飯町にあるバイオガスプラント(写真提供:コープさっぽろ、エネコープ)
コープさっぽろは2000年代から環境事業にも参入。リサイクルセンターの設置、環境配慮型店舗の開店に続き、大規模な太陽光発電であるメガソーラー、牛糞(ふん)尿と食品残さを使ったバイオガス供給にも参入してきた。「原発再稼働反対」を決議している組合員の意向も反映しているが、「反対」論を唱えるだけでなく、実践して採算性も考慮して事業化していく。組合員の囲い込みには直接的にはつながらないが、地域での地位を確立していく。
コープさっぽろは90年代末に厳しい経営状況に陥り、組合員などから有形無形の支援を受けた。組合員への恩返しとして社会貢献につながる環境事業に参入してきた。まず、組合員から廃食用油、飲料缶、紙類、トレーなどを集め、処理して販売するリサイクルセンターを08年から稼働させて対応した。
10年には二酸化炭素削減と省エネルギーを目指す、ECO・OP(イイコープ)店舗をオープン。第1号店は札幌市内にある「西宮の沢店」で間伐材を使い、外壁には太陽光を利用するヒートポンプや店舗の屋上に太陽光発電のパネルを設置した。ランニングコストは同規模の店舗に比べて年間600万円と大幅に下がっている。
西宮の沢店の後、間伐材を使わないなど、一部の設備を除いてほぼ同じコンセプトで、「さつない店」(10年11月)、「新橋大通店(釧路市)」(11年5月)、「とんでん店(札幌市)」(11年12月)、「びほろ店(美幌町)」(11年12月)を開店させていった。そして、12年、西宮の沢店に次ぐ、二酸化炭素削減と省エネルギーをめざす、ECO・OP店舗の第2号店として「いしかわ店(函館市)」(12年11月)をオープンさせた。環境配慮型店舗は合計で6店、そのうちECO・OP店舗は2店舗。これらの店舗で培った省エネ機器の効果などを把握して、他の店舗にも順次波及させていく。
◆「ガスの供給へ」
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、コープさっぽろの子会社エネコープ、酪農学園大学は11年からバイオマスエネルギーの活用に着手。北海道の一部で水質汚染などが問題となっている牛糞尿に食品生ごみなどを混合したバイオガス製造技術の開発を行ってきた。14年3月まではNEDOが運転資金を補助していたが、経済活動として自立する段階にきている。コープさっぽろは秋からバイオガスの活用を本格的に始める予定。
畜糞バイオガス製造プラントではガスの生産性を高めなければ採算がとりにくいという課題があった。今回のプラントでは牛糞尿に食品生ごみなどを混ぜることで生産性を高めた。プラントはメタンガスの生成が中心で脱硫することで通常の天然ガスと同じように使える。また副産物として液体肥料も産出している。
ガスは低圧状態で運べるようにして店舗に運搬、店舗では通常のガスと同じように使う。料金も北海道ガスと同レベルの価格で買い取る。だが、このままではエネコープ社の赤字が膨らんでいくので、コープさっぽろは採算がとれる方法を検討中だ。
◆「電力の供給も」
コープさっぽろの100%子会社エネコープは14年3月に帯広市内の巨大な太陽光発電設備であるメガソーラー施設を完成させた。出力1.21MWと0.75MWの2基に分かれ年間発電量はそれぞれ135万kW時と82.4万kW時。全量、北海道電力(北電)に売電する。
建設費7億5000万円のうち3億円を組合債で賄った。組合債は上限10万円で募集。再生可能エネルギーを望む組合員への要求に応えた。生協は不特定多数の消費者に商品やサービスを提供できず、発電事業では、組合員以外の消費者も北電の電力を使うため、組合員への還元という位置付けが難しかったため、「コープさっぽろが使う電力量までの発電量」と行政から要望があったという。
現在はFIT(固定価格買取制度)などを活用してエネコープが通常の料金よりも北電に高く売り、コープさっぽろは店舗などで通常価格で使っている。再生可能エネルギーに取り組むコープさっぽろに対して組合員からは感謝の声が上がっているという。さらに組合員から「自宅の太陽光発電の電力を購入してほしい」「電力も売ってほしい」などの要望も出ていて、コープさっぽろは発送電分離など行政の新たな動きをみている。
◆「日本生協連も発電事業に」
日本生活協同組合連合会は、原子力発電に頼らないエネルギー政策の実現と持続可能な社会を目指す立場から、再生可能エネルギー普及の一環として、2012年度から全国7ヵ所の物流施設に太陽光発電設備の設置を進めてきたが、14年6月にはFIT制度を活用する子会社の地球クラブを設立。地球クラブが日本生協連の施設も含めて再生可能な資源で発電した電力を買い取り、日本生協連などに販売する。そのため、日本生協連は物流施設の太陽光発電設備などを増強していく。

折りコンで回収する

折りコンで回収した紙などを圧縮
コープ中国四国事業連合(CSネット)は広島・尾道にある物流センターで組合員が宅配の注文に使った商品案内などのリサイクルに取り組む。組合員の環境意識の高まりを受けて事業者としての社会的責任を果たす。そのために2013年7月にエコセンターを開設。中国地区の5生協58事業所が集めた商品案内、組合員が注文に使うOCR用紙、卵パック、トレーなどを分別、圧縮して、有価で業者に引き取ってもらう。その売却益は組合員に還元していく。
CSネットのリサイクルの仕組みは簡単だ。宅配事業は各生協の配送センターから週に一度商品と次週の商品案内を届けているが、組合員からは不要になった商品案内、卵パックなどを回収。それを宅配用の車のなかで分別し、商品の搬送に使った折りたたみコンテナ(折りコン)にためていく。折りコンに入った商品案内などは配送センターからCSネットの物流センターに運ばれる。物流センター内にあるリサイクルセンターでは分別を徹底して圧縮していく。
作業は折りコンによって効率が上がった。もともと中国地区の5生協は組合員から使用済みの商品案内、OCR用紙を回収していた。各生協と取引のある引き取り業者によってフレキシブルコンテナ(フレコン)での納入を求める企業もあったが、フレコンでは宅配用のトラック内で作業できないという課題があった。エコセンターの稼働に合わせて全て折りコンに統一。エコセンター内でも折りコンのサイズに合わせて、作業しやすいようにしてある。
この仕組みは有価で衛生的に問題ないものしか回収していない、物流・配送の戻り便を活用している--などが特徴だ。有価物のみを回収するのは、逆有償となると廃棄物扱いとなり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で規制され、運搬、処理の許認可が必要となるためで、組合員が洗っていたとしても飲料容器を回収すると臭いが残り、食品を扱っている車や物流センターとしては扱いづらい。
生協は組合員が出資した組織なので、売却益を組合員に還元しなければならない。エコセンターは人件費、設備の減価償却費などを除いて各生協に還元。各生協はポイントや牛乳の値引きなどで対応している。