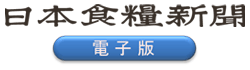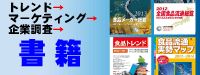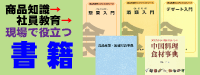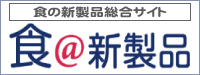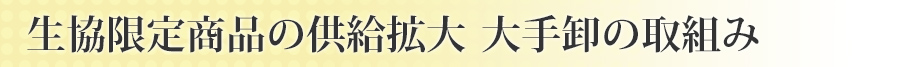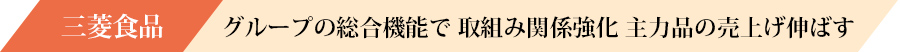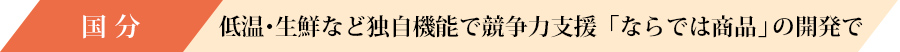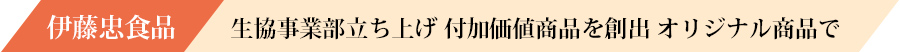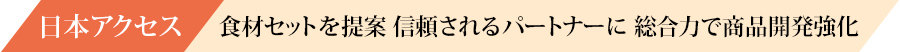食品卸は生協について、他の小売業と比べ、付加価値が高められる取組みがしやすいパートナーと位置付ける。このため生協向けには、一般チャネルとは異なる価格帯や品質の限定商品を開発・供給する動きを活発化させ、その領域は従来からの常温加工食品だけでなく惣菜デリカ、生鮮品などへも広がり始めた。今後も高齢化や有職主婦の増加などで、宅配事業を中心に生協に対する消費者のニーズが高まっていくとみている。大手卸各社の生協へ対応状況、今後の展開をまとめた。

三菱食品は生協との取組み強化へ向け、これまで以上に三菱商事グループの持つ機能を活用した提案を行っていく。従来の商品や企画提案にとどまらず、土地や車両などのサポートも行っていく考えだ。競合卸を大きく凌ぐフルカテゴリー機能を生かした宅配事業・店舗双方へのサポート強化、組合員向けに独自の販促キャンペーンなどにも注力し、今期は生協チャネルで前期比1%増の堅実な売上げを目指す。
同社は加工食品・低温・酒類・菓子の全商品カテゴリー横断型で取引先へ対応する営業組織体制に加え、三菱商事の商社機能やグループ企業のノウハウを活用した包括的な顧客支援を行っている。
生協チャネルに対してもそうした総合力での競争優位性を前面に出すことで、一段と取組み関係を強化する考えだ。これまで三菱商事グループの持つ機能を十分に取引先へ提供しきれなかったこともあり、「特に生協は現場の実務責任者向けには定期協議会などで提案してきたが、理事長・専務など経営マネジメント層には当社の持つ機能を十分にご理解いただけてなかった」(同社・高橋文雄営業第一本部第五グループマネージャー)と反省。
このため4月から同社の営業やマーケティング、物流担当者などが一体となって、全国の生協向けに“三菱食品の機能プレゼン”に着手。これまでコープ九州、コープネット、ユーコープのトップなどを訪問し、それぞれ長時間の濃いプレゼンを実施したという。
プレゼンでは従来の商品や物流といった卸レベルの提案だけにとどまらず、三菱商事グループの持つ包括的なソリューション機能を説明。たとえばセンター建設のための土地活用、宅配事業向けのトラックやタイヤの供給などで役に立てる提案のほか、三菱商事の原料調達力を生かした店舗向へのカウンターコーヒー提案など、以前はできなかった機能紹介などを実施。生協の意見や要望なども聞き、相互の関係強化へ努めている。
今期の生協向けの事業戦略テーマには(1)新たな売り方・売場提案(2)主力商品のさらなる拡売--を挙げる。このうち売り方提案で重視するのが、フルカテゴリー機能を基軸とした宅配事業の買取りチラシの強化だ。「競合を凌ぐ当社のフルカテゴリー対応力を生かし、バランス良く内容を充実した企画を任せていただけるよう強みを訴求していく」(同)と狙いを語る。
その具体事例として、5月からコープネットの宅配事業向けに「地中海式食生活」の提案を実施している。オリーブオイルやイワシ缶詰、パスタなどヘルシーで栄養バランスの良い食材を組み合わせた地中海メニュー「いわしのスパゲッティ」を管理栄養士の監修で企画。レシピや商品企画をカタログに掲載し、組合員の購買意欲の喚起を図っていく。この企画はスポットでなく、年間を通して定期的に実施する計画だ。
主力商品の強化を重視するのは「前年実績をクリアするには同じ提案をしていては難しく、需要創造への取組みが不可欠だ。組合員の購買意欲を促進し、売れ筋商品の数字を効果的に伸ばす仕掛けを打つことが供給拡大へ貢献できる近道」(同)との考えによる。
それに向け、主力商品を使った「アレンジクッキング」の提案へ取り組んでいる。例えば「吉野屋の牛丼の具」を使った“牛丼パスタ”の提案により、パスタはもちろん唐辛子や乾燥ネギなどの関連商材の売上げも伸ばす。トマトソースやチーズをギョウザに乗せて焼く“ギョウザピザ”などのアレンジメニューも同様の狙いで開発。

菓子ではカスタードケーキを使って主婦と子どもが一緒に楽しんで作る“フラワーケーキ”を提案している。このメニュー提案でも自社のフルーツ缶詰やホイップクリームなどを組み合わせ、効果的に売上げを伸ばしたい考えだ。
主力品強化の一環として、配達員が組合員に商品を薦める“声かけキャンペーン”も展開している。「生協で組合員に接することができるのは配達員の方だけ。(配達員が)組合員の方々に少し商品の説明をするだけで、売上げが大きく変わってくる」(同)。
キャンペーンを効果的に推進するため、三菱食品は生協の配送センターで配達員向けに拡売対象商品の試食や調理実演などを行い、実際に商品の良さを知ってもらい販促に役立てる。5月はこのキャンペーンで、ギョウザ22万パックを販売するなど顕著な成果も得た。
同社の2013年度3月期の生協チャネル実績はトータルで前期比4%増の順調な伸びを示した。店舗は生協の動向を反映する格好で厳しいが、宅配向けは好調な動きという。「生協の宅配事業そのものもネット通販などの影響を受けているが、新たな策を投じればまだ伸びる。当社もさまざまな機能を提供し、一緒になってお役に立てる方法を考えていく」「鍵を握るのは生協限定商品、差別化商品をどう売るか。当社の機能をフル活用していただき、相互に成長を継続したい」(同)など、今後の展望を語る。(篠田博一)

国分は開発育成メーカーとの幅広い関係や強化を進める低温・生鮮分野など、独自の卸機能を駆使して、生協との取組み関係を強化する。好調な宅配事業向けに生鮮・惣菜キットや地場メーカーと開発したこだわり商品などの供給を加速するほか、店舗にはエリアMD、コープブランド・NB商品を最適に組み合わせた売場提案へ取組み、生協の競争力をサポートしていく。
生協向けの商品開発の基本スタンスは、組合員に対して明確な差別化を訴求できる“生協ならではの商品”に重点を据える。「生協は通常の量販店では売るのが難しい商品でも、紙面の中でストーリーや価値、こだわりなどを伝えられるので販売しやすいのが特徴」(同社・前原康宏関東支社第一営業部長兼広域統括部スタッフ)として、地域メーカーなどと連携して付加価値商品の供給に努めている。
すでにカタログ販売などで数量限定の水産缶詰やこだわりの日配品、和菓子など計画を超えるヒット商品も生まれ、今後も生協限定・専用の規格・容量による“ならでは商品”の開発を加速する考えだ。
国分の前12月期の生協宅配事業への売上げは好調に伸びた様子で、同事業向けに特別力を入れていくのが、生活者ニーズの高まっている惣菜キットなど低温商品の供給だ。「従来、当社は生協へも酒類やドライの供給が中心だったが、先行する競合に並ぶ機能構築」(同)も目指し、昨今は急速に低温流通のノウハウ蓄積やインフラ整備を進めている。
生協の宅配は以前は週1回配送が主流だったが、最近はネット通販などに対抗し、「夕食宅配」など毎日配送や週5回配送へ取り組む動きも増えてきた。そうした市場の変化も受け、カット野菜や魚の切り身など対応の幅を強化。東京青果や八社会といった有力青果物卸との提携関係も生かし、宅配向けに協業を進める計画もある。
一方、苦戦が続く生協の店舗事業向けには、エリアMDを軸に競争力をサポートする考えだ。オーバーストアや異業種参入などで小売市場の店舗間競争が一段と激化する中、地域によって異なる売れ筋に対応した品揃えや売場作りを的確に行うことは、極めて重要な課題といえる。
国分では県ごとの消費動向などを緻密に分析した上で、店舗規模なども考慮したサポートを志向。特に生協は180~800坪など店舗によって規模のバラツキが大きいため、小型店や中型店など店ごとの特性に合わせた売場作りや販促提案に努めている。
基本的にはコープブランドを主軸に置き、その店舗のニーズや課題に応じた差別化商品、収益商材をいかに揃えるかを重視。自社ブランドの「K&K」のほか、開発育成メーカーの個性的な商品供給などに努めている。またNBメーカーの新商品などをタイミング良く効果的に売るために、フレッシュ感を意識した売場作りへ取り組むのも重要なポイントという。
宅配、店舗の双方の事業をサポートする機能として、独自のトレンド予測による提案も強化。年間を通してハレの日メニューや絆作りといったキーワードを設定、それを企画や商品レベルまで落とし込み、生協の売上げ増へ結びつける取組みだ。
国分は生協のチャネル特性を「シニア層の増加など高齢化が進行する中、有望視している。異業種の攻勢は厳しいが、商品の価値をしっかり伝えられる販路であり、価格軸だけに限定されないのが生協の特徴と思う。意識の高い組合員の方々も相当数が加入している」(同)とみており、今後も取組み強化へ向けて多様な機能を追求していく考えだ。(篠田博一)

伊藤忠食品の掲げる中期経営ビジョンは「卸機能日本一のグッドカンパニー」。常に変化する環境の中で、成長を続けていくために、優良顧客との取引の深耕、価値ある商品の調達・発掘、新規事業の拡大を重点施策としている。その施策を支えるのが「オリジナル商品」群。このオリジナル商品戦略は、他大手卸と比べ、極めて個性的だ。人気外食チェーンや有名シェフなどのブランドオーナーとタイアップしたオリジナル商品=ブランド開発商品に特化し、競合にはない付加価値の創出を目指している。
戦略商材「ブランド開発商品」には、二つのベクトルがある。一つは、「身近で普段から馴れ親しんでいるブランド」を中心にしたもの。もう一つは、老舗や三ツ星レストランといった日常的には味わえない、憧れのブランド。この「ちょっとした贅沢」を同社の開発商品として比較的手軽に提供しようとした。このオリジナル商品の最大の得意先が生協業態。ブランドの世界観が伝えやすい共同購入は商品の特徴が伝わりやすく、また、少し高くても安全・安心でおいしい商品を求める組合員向けには、同社ブランド開発商品のターゲットにもぴたりと当てはまる。現在、生協共同購入向けの開発に取り組んでいる。
現在の生協業態との取引状況は全社約150億円。その大半が近畿圏での実績で、エリアベンダーとして、「コープこうべ」「コープきんき」を主とした取引。カテゴリーは、加工食品、酒類、冷凍・チルド、ギフトなど多岐にわたる。西日本営業本部は長年の取引の実績から、「コープこうべ」「コープきんき」への差別化商材、全国発掘商材の提案を重ね、その提案力は両組合からも支持されている。この機能を全国の生協へ広げるため、13年11月に「生協事業部」を立ち上げ、全国を全社的にサポートする体制を構築した。西日本の生協向け提案営業のスキーム、商品調達力を全国の営業本部と共有し、効果的な取組みが提案できるように設立した組織だ。生協では、事業連合の結成、共同仕入れの実施、事業体の合併など、各生協が進める競争力強化に向けた取組みが活発化している。今後、西日本だけでなく、東海、東日本でも各生協の支援を進めていく。
また、提案力強化に向けた取組みとして、全国の生協担当者が集まる「生協事業部会議」を開催し、安全・安心でおいしい価値ある商品を中心に、各担当者が発掘した商品の提案事例・成功事例を共有している。今までは3ヵ月に一度の頻度だったが2ヵ月に一度に変更することで、より情報共有を密にして、スピード感を持って提案を進めていく。また、生協事業部メンバーが全国の生協トップへのアプローチを行うことで横展開をサポートし、今期、各生協との取組みの強化、取引カテゴリーの拡大を目指す。
同社が注力カテゴリーとして進めるサーバー管理型プリペイドカードも導入が進む。13年11月には、全国の生協業態で初の店頭展開を、みやぎ生協で導入。46店舗全店で、52券種取扱いしている(うち全国お取り寄せスイーツなど同社発行カードは8券種)。GMS、コンビニではすでに導入されているがSMでは導入例が少なく差別化が図れる商材として注目されている。また、主に若い層が購入しているiTunes Card、ニンテンドーカード、Amazonギフト券などの取扱いで、生協業態が弱いといわれる若い層を取り込める可能性が見込め、生協サイドからの期待がかかっている。
「得意先、メーカー、消費者、われわれが共に幸せになる新しい価値の創出に挑戦していきたい」(魚住直之本部長)としている。(田中秀哉)

日本アクセスは、日本生活協同組合連合会や各事業連合、各生協などに冷凍・冷蔵食品、常温流通商品をはじめ生鮮食品も幅広く提案している。今期は得意とするスイーツはもとよりチルド包装惣菜や冷凍食品などアクセスブランドを中心に提案強化を図っていく。
同社の14年3月期連結売上高は前年比5.7%増の1兆7140億3800万円だった。うち、生協関連の売上高(日本アクセス北海道を含む)は前年比4.9%増の455億円規模となる。
広域営業本部生協営業部の松岡正進部長は近年の生協について「以前はPBといえば生協だったが、近年大手小売のPBが増加し、生協PBを脅かす存在になってきた」という。店舗についてもSMだけでなくCVSやドラッグストア、ディスカウントストア店など競争激化で「店舗を取り巻く環境もいよいよ厳しくなってきている」。
こうした中で同社では、各生協向けの商品発掘や開発に軸足をおいてきた。価格競争からの脱却を目指し、「生協でしか買えない」「生協ならでは」をコンセプトにメーカーと協働し商品開発・提案を強化している。
また、生協は宅配のパイオニアでもあったが「ネットスーパーの台頭や、GMS、CVSの配達サービスの仕組みができており生協チャネルもここが正念場」(松岡部長)。生協の宅配は、週1回の配達が基本で特に冷凍食品が強かった。しかし、ネットスーパーは翌日配達が進んでいる。これに対応し、毎日配達が構築されている生協向けに、日本アクセスでは日配品を組み込む戦略を進める。
特に食材セットの成長が顕著だ。「ファミリー層では忙しいお母さんが簡単に料理できる。高齢者は食材の廃棄を避けられるため需要が高い。そして何よりもおいしい」(同)。
食材セットは昨年2月から提供を開始。サンドイッチや麺類、チルド惣菜などすぐに食べられるものを含め現在200アイテムを扱い、今期は10億円超の売上高を目指す方針だ。
同社では、安全・安心を担保する食品安全管理部と、生鮮食品の調達力を発揮する生鮮・食材MD本部を組織する優位性をフルに生かし、総合力で今後も商品開発に力を入れていく。取り扱いが少ないドライ食品分野では乾物・乾麺などアクセスブランドを中心に提案を強化する。
同社は商品提案だけではなく得意先の省力化のためのソリューション提供にも注力している。その一環として、店舗のPOSデータを元にした需要予測・自動発注システムを構築することで流通各層の需給ギャップを解消し、ロスの削減・全体最適を実現する「ジョイントフォースDCM」の導入推進により受発注コストの削減提案を実施。
すでにコープこうべで導入され、省力化に貢献。日配品ではその効果が顕著に表れ、商品ロス率や在庫の廃棄、省エネなどの環境対応、流通全体最適化や食の安全管理といったさまざまな課題を「支援」するだけでなく、具体的に「解決」まで導いている。
今後の生協事業の取組みについて松岡部長は「生協の組合員は食への関心はもとより環境保全の意識が強い。当社の新企業理念の使命である“まもる。つなぐ。つくる。”を実現していくことで、組合員の満足度向上を図り、各生協から信頼されるパートナーになりたい」と強調する。(山本大介)